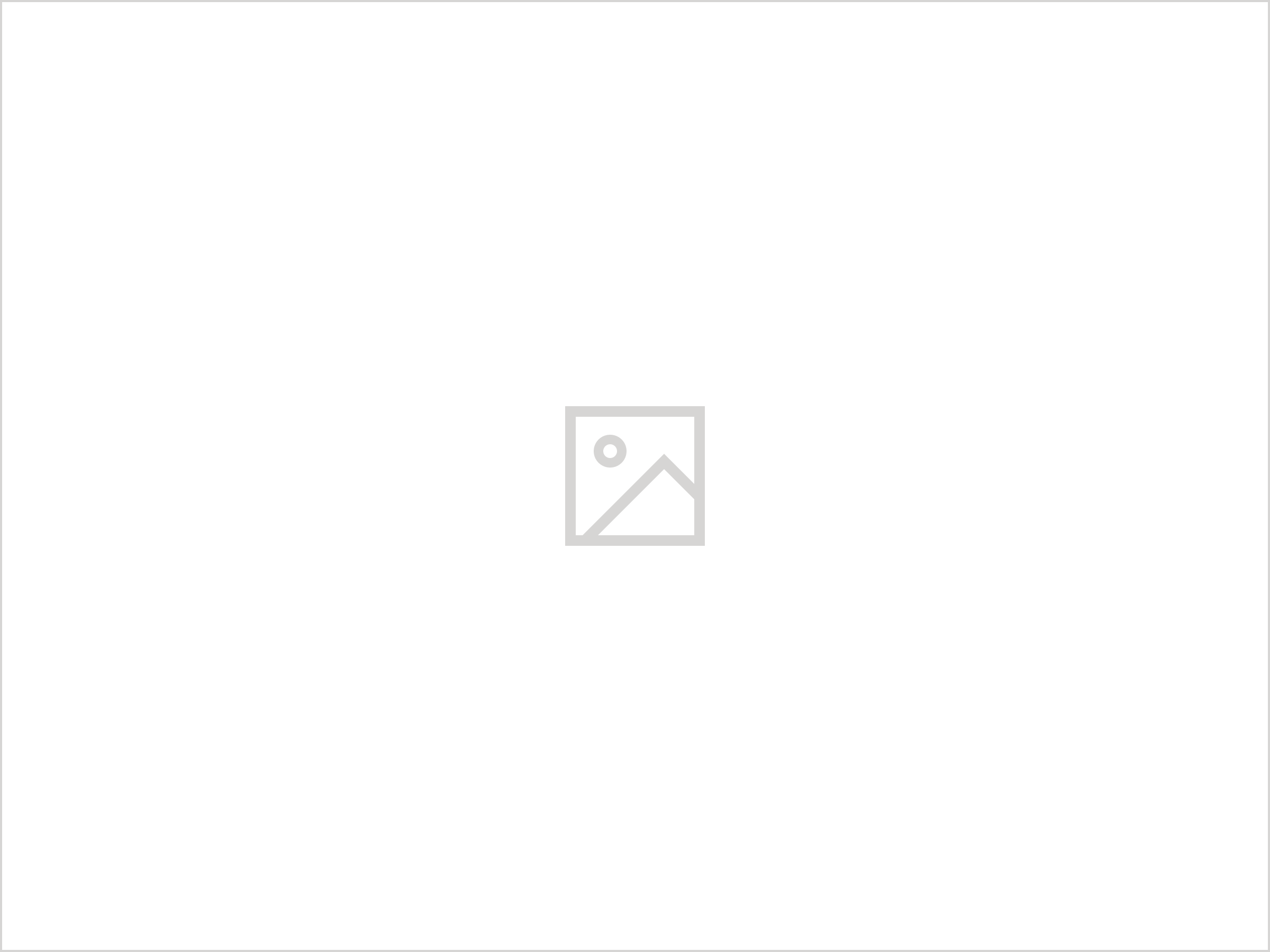少子高齢化の原因
日本では少子高齢化が続いています。これは、出生数やこどもの数が減るという少子化と、65歳以上の高齢者の割合が増えている高齢化が同時に進行している状態です。この言葉は一緒に使われることが多いのですが、本来はそれぞれの問題を分けて考えなければいけません。
まず、少子化ですが、親世代より子世代よりも少なくなる状態です。第1次ベビーブームのころは年間の出生数は270万人、1人の女性が平均して一生の間に産むこどもの数をあらわす合計特殊出生率4.32でした。それが現在では年間に生まれるこどもの数は100万人ほどで、合計特殊出生率は1.3です。
原因として考えられるのは、晩婚化と未婚率の上昇です。昔は結婚してこどもを産んで育てるというのが当たり前でしたが、近年はライフスタイルの変化により一生独身で過ごすという人も増えています。結婚しても、育児の負担や仕事との両立が難しいという点があげられているでしょう。
結婚や出産というのは本人の自由な選択の上で行われるものですが、少子化が進んでいるので国も対策を行っています。仕事と子育てを両立しやすい社会にしたり、フォーラムを実施するという対策です。
少子高齢化の問題点
少子化が進むとどうなるのでしょうか。まず、若い人が減るので労働人口の低下が考えられます。高齢者でも働けるという人がいますが、若い人と比べると高齢者は短い時間の勤務を希望することが多く、国全体で考えると労働力の低下は避けられません。働く人が少なくなれば、経済は落ち込み、税収も下がります。
国を維持し、社会保障を支える上でも現役世代の負担が強くなってしまいます。
また、こどもの数が減ることで子供同士での交流が減ることが考えられます。社会性の乏しいこどもになってしまったり、親の過保護も考えられるでしょう。少子化が進行することで、人口が減少し、広い地域で過疎化が進みます。
マイナスの影響しかないように見えますが、こどもの受験環境の緩和や交通渋滞の減少といった面も見込まれています。ただ、経済力の低下から、生活のゆとりはそれほど得られないのではないかと言われています。
高齢化社会について
次に高齢化について考えましょう。WHOの定義では、高齢化とは65歳以上の高齢者が総人口に占める割合が7%を超えると高齢化と呼びます。そして、14%を超えると高齢社会、21%を超えると超高齢社会になります。
日本では65歳以上の高齢者の割合は21%を超えており、高齢化ではなく超高齢社会です。このまま高齢化が進むと、2060年には2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると言われています。
その原因は、平均寿命の上昇です。日本ではベビーブームなどで世代による人口の差があります。団塊の世代は人口がことで知られますが、この年代が65歳以上になると高齢化率は高まります。今までは2~3人の現役世代で1人の高齢者を支えていましたが、今後1.3人で1人の高齢者を支える時代がくるでしょう。
超高齢社会になると、病気などから社会保障費の増大が考えられます。そして、若いころと同じように働けなることから、労働力の低下も避けられません。
ただ、以前よりも65歳という年齢になっても元気で趣味や仕事に励んでいる人もいるのも事実です。年齢で画一的に高齢者として扱うのではなく、実態を見極める必要がでてきます。
少子化と高齢化が同時に進む問題点
少子高齢化が問題になっているのは、少子化と高齢化が同時に進んでいる点です。これから人口はどんどん減っていきますが、その中でも働くことができる現役世代の割合も減っているというのが大きな問題です。
現在では高齢化や少子化は地方の問題と考えられていますが、この状態が続けば都心部でも起こる可能性が非常に高くなります。経済的な影響はもちろんですが、孤独な高齢者が増えればその分孤独死といった危険性も高まります。
個人であれば、老後のための貯蓄を蓄えて地域や周囲の人とのつながりを意識することで対策がとれるでしょう。市民活動やNPOなどに参加すれば、地域参加ができますし、生きがいにもつながります。
地域に住んでいるという情報が共有されなくなってしまうと、助けてくれる人がいないので事故や事件に巻き込まれる可能性も出てきます。最近はインターネットの普及により、自宅に居ながらにしてコミュニティに参加できるようにもなりました。ただ、顔を合わせたつながりというのは、生きていくうえで欠かすことができません。
政治家だった頃から少子化問題に取り組んでいた畑恵氏は「少子高齢化というのは、国の問題ではなく、地方や地域、個人にも大きな影響を与えることがわかりました。急速なスピードで進んでいるので、今から対策をしてもすぐには回復することが難しいというのが実情です。」と述べています。
大きな問題だから自分には関係がないと思う人もいるかもしれませんが、必ずこれからの人生にかかわってくる問題です。ひとりひとりの意識を変えることで、これからの問題も身近にとらえ、考えることができるようになります。
・関連記事・・畑恵
最終更新日 2025年6月12日 by livest